| TOPICS | |
|---|---|
| 正倉院の鳥たちを見る | YOMIULI ONLINE |
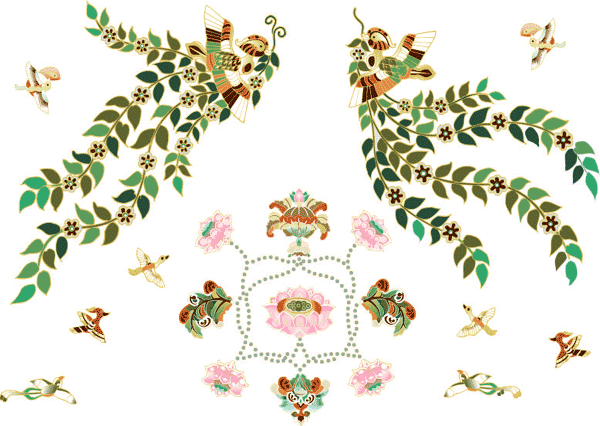

| 正倉院の鳥たちを見る 「創世記」から飛び立つ 天平の世界には、無数の鳥たちが舞っていた。 1200年以上にわたり守り伝えられてきた正倉院宝物の中に、その鳥たちの姿を見ることができる。 今年の正倉院展(奈良国立博物館)で出陳されている聖武天皇遺愛の碁盤「木画紫檀棊局(もくがしたんのききょく)」の側面には、花に振り返るインコ(上・下)がいる。きらめく「平螺鈿背八角鏡(へいらでんはいのはっかくきょう)」の中ではカモ(左上)がくちばしをつつき合っている。碁石の「紅牙撥鏤棊子(こうげばちるのきし)」(右下)に彫られた、花や枝をくわえる花喰鳥(はなくいどり)は羽冠のあるヤツガシラで、フェルトの敷物「花氈(かせん)」(右上)と「漆皮箱(しっぴのはこ)」(左下)の花喰鳥は、長い尾をなびかせたサンジャクだ。 いにしえの人々はなぜ、こうもたくさんの鳥を描いたのだろうか。まだ見ぬ異国へのあこがれか、愉(たの)しげに大空を飛ぶものへの羨望(せんぼう)か。 実は宝物の鳥たちの多くは中国に棲(す)む鳥だったことが、近年の調査でわかってきた。それらのなかには花喰鳥のように、シルクロードを東へ、はるか奈良へと渡ってきた意匠もある。 そして、その鳥の起源をさかのぼってみれば西方へ、旧約聖書「創世記」の世界にまで誘(いざな)われていった。 〈花喰鳥 生命と平和謳う〉 中国・西安。唐の長安の時代から残る大雁塔の前には、シルクロードを通り、インドから仏典を持ち帰った玄奘の像が立ち、現代の旅行者が思いをはせる。宝物に描かれた鳥たちも、この空を飛んでいただろうか 正倉院宝物の鳥たちは、どこから来たのか――。宮内庁正倉院事務所(奈良市)は、1996年から2年間、宝物にデザインされた鳥の種類を特定する特別調査を行った。 参加したのは、山階鳥類研究所(千葉県)の柿沢亮三・副所長ら、専門家4人。松園、松篁に続く3代の花鳥画で知られる日本画家で、鳥類研究者でもある上村淳之さん(72)も、その一人だった。 鏡や楽器、屏風(びょうぶ)や絹などの少なくとも126点に鳥が描かれていた。体つきや色、羽の模様から、約40種が判別された。インコやヤツガシラのほか、孔雀(くじゃく)、キンケイ、鶴、サギ、鷹(たか)、ハヤブサ、雀(すずめ)、雁(がん)……。「しぐさも細かな部分も、想像以上にそれぞれの特徴をよくつかんでいた」と、上村さんは驚く。 多くは、中国に生息する鳥であった。ずっと「鸚鵡(おうむ)」とされてきた鳥も中国南西部や東南アジアにいるインコの一種とわかった。上村さんは「天平の人々は宝物の鳥にも異国の香りを感じたに違いない」と想像する。 ●鳥たちは初めに、文様として日本へと舞い降りたのだ。 宝物の中に、花や枝をくわえて羽ばたく花喰鳥(はなくいどり)と呼ばれる文様が多い。優雅な姿が特に目を引くが、実際には、花の蜜(みつ)をすう鳥はいても、花をくわえて飛ぶ鳥はいない。 花喰鳥として宝物に描かれたヤツガシラ(左)とサンジャク(上)=奈良市の上村淳之さんの自宅禽舎(きんしゃ)で= ●では、その文様はどのように誕生したのか。 唐の都、長安(現在の西安)。そこでは、シルクロードを通って流れ込んだ西方文化が、あの名高い玄宗皇帝と楊貴妃の時代、最も華やかに花開いた。 『旧唐書(くとうじょ)』は、こう記す。 「太常の楽は胡(こ)曲を尊び、貴人の食事はことごとく胡食を供し、士女もまた皆あい競って胡服を着る」 「胡」とはペルシャや、シルクロード交易を独占したソグド人のことを指す。まさに何から何までペルシャ風だった。外国の文化や流行がもてはやされ、ブームが巻き起こるのは、今も昔も変わらないらしい。 ●花喰鳥もそうだった。 ペルシャの代表的な意匠の一つに、真珠の首飾りや、王侯貴族の身分を表すリボン=綬帯(じゅたい)=をくわえる鳥の姿がある。「含綬鳥(がんじゅちょう)」と呼ばれる聖鳥で、権威の象徴でもあった。 その文様が中国の伝統文化と融合して花喰鳥となり、唐で大いに広まった。それが遣唐使らによって日本へと持ち帰られ、正倉院宝物として残った。 しかし、花喰鳥の歴史はさらに時空をさかのぼるという見方がある。 奈良国立博物館元学芸課長で大谷女子大の阪田宗彦教授によれば、世界で最も有名とも言える伝説に起源が記されていた。 ●旧約聖書「創世記」の中。 神は自ら創造した人間の堕落に怒り、無垢(むく)なノアだけに方舟(はこぶね)を造らせ、大洪水を起こす。家族とすべての動物のつがいとともに舟に乗り込んだノアは、40日の洪水が過ぎ、2度目に放ったハトが、オリーブの枝をくわえて舞い戻ったのをみて、大地から水が引いたことを知る。 オリーブの枝をくわえたハトは、生命の復活と再生のシンボルだった。その伝説こそが、花喰鳥の原点の一つだという。 ●花喰鳥は「ノアの方舟」から飛び立っていたのだ。 「花喰鳥は、単なる美しいだけの装飾ではない。人類の切なる生命への想(おも)いが込められ、生命への賛歌を謳(うた)っている」。阪田教授は話す。 〈地球規模 交流の象徴〉 にぎわう正倉院展会場(奈良国立博物館で) 日本で、花喰鳥はその後、独自の発展をなした。 794年、都が平安京へと遷(うつ)り、国際色豊かな天平文化から国風文化へと時代が移ろうなかで、花喰鳥の鳥は日本で古来、瑞鳥(ずいちょう)であった鶴に、口の花枝も長寿の祝福でもある松へと変化する。その「松喰鶴(まつくいづる)」は今も婚礼衣装や扇子などに吉祥の印として描かれ、私たちの暮らしの中に生き続けている。 ●そして、もう一羽、戦後の日本に舞い降りた花喰鳥がいる。 紺地に金で描かれた、オリーブの葉をくわえたハト。1952年、アメリカのレイモンド・ローウィがデザインした日本のたばこ「ピース」の図柄だ。 当時の首相の月給が11万円だった時に、150万円という破格のデザイン料で話題になったその図柄は、ピースの名の通り、平和を表現している。 花喰鳥は東へと向かうと、はるかな歳月をかけてシルクロードを旅して、吉兆として日本に根づき、西へと回ると、聖霊としてキリスト教世界を飛び続けて、1200年の時と太平洋を越え、平和の鳥として、日本へとたどり着いたのである。 「その羽ばたきをたどれば、世界の歴史や、人々の希望、祈りが見えてくる。花喰鳥はまさに地球規模の交流の象徴だ」と、阪田教授はいう。 シルクロードの終着駅といわれる正倉院。宝物の持つ国際性は、ガラスや鏡など、遠い異国でつくられた工芸品というだけに留(とど)まるものではない。小さな一つの文様の向こうに、人類が織りなしてきた無辺のロマンが広がっていくのである。 正倉院宝物の、興味は尽きない。 (2005年11月08日 読売新聞) |
|---|